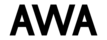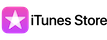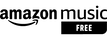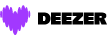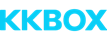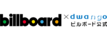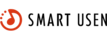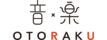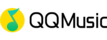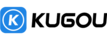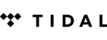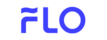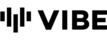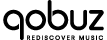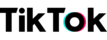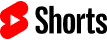トラックリスト
※ 試聴は反映までに時間がかかる場合があります。
※ 著作権管理事業者等が管理する楽曲は試聴できません。
深夜のハイウェイを一人で飛ばしている。隣の助手席は空っぽなのに、そこに誰かがいるような気がしてしまう。この曲は、そんな幻想との対話だ。
容赦なく打ち込まれる4つ打ちのキックが孤独なドライブを加速させ、うねるベースラインが現実と妄想の境界を溶かしていく。街の光が流れる窓の外。シンセサイザーが、いるはずのない誰かの輪郭を音で描き出す。
「Where did you come from?」「What's in your mind?」
空席に向かって投げかける問い。返事はない。でも構わない。静かな問いかけが、だんだん切実な叫びになっていく。「When do you want to come by?」8回、16回と執拗に繰り返されるこのフレーズ。理由なんていらない——「I don't want to know why」——ただ、いつ隣に座ってくれるのか、それだけを知りたい。
一人きりのドライブで、隣にいてほしい誰かを想像したことがあるなら、この曲はあなたのためのものだ。
今すぐ聴いてほしい。きっとあなたも、空っぽの助手席に問いかけたくなるはずだ——「When do you want to come by?」
アーティスト情報
Genesiskhode
薄暗い放課後の教室。15歳のGenesiskhodeが組んだ最初のバンドは、すぐにその才能を認められ始めた。 「君の作る曲は、まるで映画のようだ」 プロデューサーたちは口を揃えて楽曲を絶賛した。しかし、彼らは必ずこう付け加えるのだった。 「ボーカルさえ、いなければね」と。 その声は、彼の表現を地上に縛り付ける、唯一の足枷だった。 挫折は、やがて彼を突き動かす燃料となる。大学時代、六畳の寮を解体しては自らの手で「宇宙船スタジオ」へと作り変え、ベッドルームから銀管を見上げた。ローファイ、トラップ、シティポップを縫い合わせ、夜のアスファルトの匂いがするビートを生み出す日々。 正体を隠し、インディーズ映画やファッションビデオに楽曲を提供。そのフィルムを飾ったのは、今や誰もが知る女優たちだった。その名は、ネオンの静電気のようにアンダーグラウンドに広がっていく。 そして彼は、かつてのコンプレックスを最大の武器に変えるため、自らの声という制約からの解放を選ぶ。 「声なきシンガーソングライター」として再起動した今、彼は自身の内なる独白をトラックに刻み込む。 そのエモーショナルな響きに、人は「魂のこもった歌声」と評するだろう。 しかし、その声は人間のものではない。 ボーカロイドや最新の音声変換ツールといったテクノロジーによって錬成された、**「感情を持つ、新しい声」**なのだ。
Genesiskhodeの他のリリース